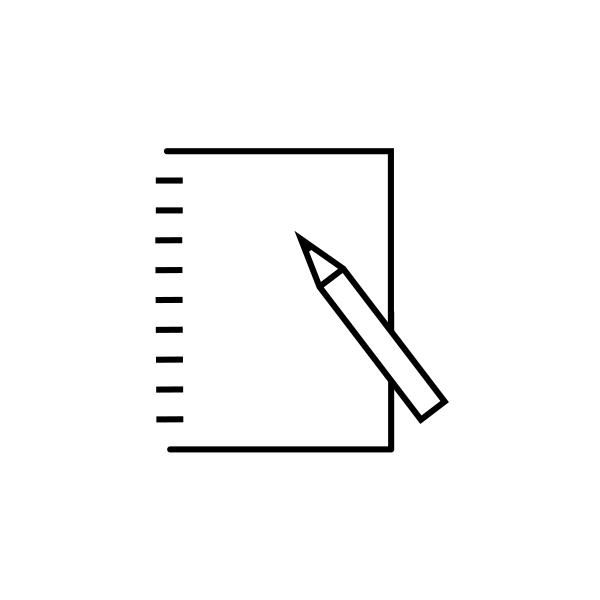映像世界を通しての「空間体験」と現実世界での「空間体験」とのギャップ
2021.03.04

映像と現実との埋められない乖離
マルチプレーン・カメラ(Multi Plane Camera)というものをご存知だろうか。 アニメーション制作といえばセル画が当たり前だった1930年代。 ウォルト・ディズニー・カンパニーによって発明された映画撮影用のカメラである。
二次元である絵を重ねたセルアニメーションでは、特に風景の描写は平面的で奥行きを表現することが難しかった。 画面の奥へ移動する描写は、平面の絵をズームインするだけなので奥行きや立体感を感じられない。
そこで、背景を深度毎にレイヤー分割して、それぞれのレイヤーとカメラの距離を調節することで、平坦なアニメーションに三次元的な立体感をもたらすマルチプレーン・カメラが開発された。
ディズニーはこのような大掛かりな装置を開発してまで、「現実世界での空間体験」と「映像の中の空間体験」との間にあるギャップを埋めようと試みていた。
その後、マルチプレーン・カメラとして最も名を馳せた映画作品が、『白雪姫』である。ディズニーが、4年の歳月と25万枚のセル画を費やして完成させた当時、桁外れの大ヒットを記録し、現在でもアニメ史に残る傑作として知られる。そのマルチプレーン・カメラの高い技術が評価され、『風車小屋のシンフォニー』は1937年のアカデミー短編アニメ賞を受賞した。
日本では、持永只仁がマルチプレーン・カメラを模倣した多層式撮影台を開発した。瀬尾光世により『アリチャン』(1940年)、『桃太郎の海鷲』(1943年)の製作に用いられ、マルチプレーン・カメラは日本のアニメ界の大きな影響を与えた。
奥行きのみならず、背景の立体感をリアルに再現することができるこの撮影方式は、アニメ界にとどまらず、テレビ番組や他の表現形態でも、マルチプレーン・カメラに関連した効果が使われている。
現実世界と映像内での「空間体験」の違い
それでは、現実世界の空間体験と映像の中での空間体験とでは具体的にどのような違いがあるのか。
現実世界での空間体験は、体験の主体である自分自身の知覚と、物や人など知覚の対象との関係性から成るものである。 久々に実家に帰った際の体験を考えてみよう。変わらない玄関、リビングでの食卓を囲んでいたテーブルがあり、自分の部屋には机が当時のまま残っている。建物とその中の家具が、かつての記憶を思い返させ、なんだか懐かしい体験ができる。これは、物との関係性が体験を形作っているからである。
しかし、もはや親がいなくなった実家に帰った場合、同じように感じることはできないだろう。建物も家具も同じでも、そこにはいるべきはずの人がいない。何も言わずに守ってくれる親の存在を感じる安心を感じられない。これは、人との関係性が体験を形作っている例である。
一方で、自分を中心とした知覚が存在しない映像の中では、映像の中の人物に自分自身を重ね、その空間を体験する。つまり、映像のなかの空間を体験するという行為は切り取られた風景の中に見える人やものを介した「代理体験」であり、映像としての「視覚体験」なのである。
したがって、映画を見る観客は自分自身の知覚を登場人物に投影するうちに、裸足でガラス片を踏みながら進むブルース=ウィルスを見て思わず顔をしかめ、地上400mある高層ビルの壁をロープ一本で駆けるトム=クルーズを見て肝を冷やしてしまうのである。 このようなスクリーンの向こう側とこちら側を行き来するような感覚こそが、映画の世界に人々が引き込まれる要因であり、日常の「空間体験」との大きな違いである。
「代理体験」での世界はどうなのか
見るものを映像のなかに没入させ、映像内の空間を「代理体験」させることが映像の中の空間体験が持つ価値であると述べたが、その例として小津安二郎の作品が挙げられる。
小津作品の特徴として、物語の舞台である日本家屋での生活を様々な視点からの映像を断片的に映し出すモンタージュと呼ばれる撮影技術によって淡々と描いていくという点が挙げられる。
舞台が細やかに分割されることで、観客の知覚は方向性を失い、映像の中の人物の行動によって空間を想像するようになる。
このように、小津により狂気的なまでに計算され尽くした映像によって見るものは無意識のうちに没入させられていくのである。
一方で、映像の中の空間体験では映像内に没入した観客を現実世界では起こり得ない事象をもって裏切ることで未知の体験を提供することもできる。
「バック・トゥ・ザ・フューチャー」や「フォレストガンプ」などで知られる映画監督ロバート=ゼメキスの1997年の作品「コンタクト」での鏡を用いたシーンがその例としてあまりにも有名である。 (https://www.youtube.com/watch?v=avRdYf78kLk )
観客はこの映像を見て、少女が廊下を勢いよくカメラに向かって駆けて来る様子から、その行き先(カメラの背後の映像)を想像する。そして、「どこに向かっているのだろう」「進行方向を写す画角に切り替わるのかな」などと無意識に次の展開を想像する。
だが次の瞬間、その一連の映像が鏡に映るものであったことに気付く。
観客は現実世界では起こり得ない現象に驚き、より一層映像に引き込まれていくのである。
これからの「空間体験」とは
現実世界と映像内での「空間体験」について述べてきたが、今や最新技術によって、それらを組み合わせた新たな空間体験をすることができる。
VR(Virtual Reality = 仮想現実)では映像の中に入り込み現実世界のような空間体験をして、AR(Augmented Reality = 拡張現実)では映像がまるで現実世界の中に存在するかのように投影することができる。
Unityというゲーム開発ツールをご存じだろうか。弊社でもUnityを利用してVRでの住居の空間シミュレーションツールを作ってみた。建物の中に自由に家具を配置して、実際に中にいる人の視点から、見え方をチェックできる。どのくらい大きなテーブルをおけるかや、邪魔にならないソファの置き方を検討できたりする。
ただ、仮想空間を、現実世界のような空間として感じされるには、知覚を刺激する、素材や形状のリアリティが必要不可欠となる。例えば、壁面の凹凸感、床のクッション性、そこに行って触れてみたかのような、知覚の体験を画面上で体験できる事が重要だ。
加えて、あかたもそこに自分が存在しているような、視点の自由度が重要である。視点の可能な範囲を広げ、できるだけ制限を少なくする事がリアリティへの近道なのかもしれない。
ところが、視点の動かし方は、現実世界と同じにしても、違和感が出てしまう。バーチャルの世界ではそのスピードが遅すぎると感じてしまい、なぜかしっくりこないのである。
不思議な事に私達は、現実世界のようなリアリティを求めているのにも関わらず、仮想空間のならではの、現実世界とのギャップを感じる事によって異世界にいる体験を欲しているのかもしれない。