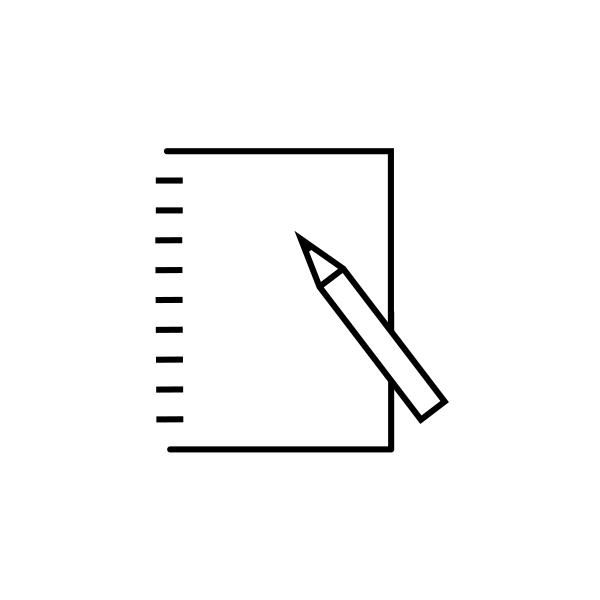思った通りには進まないデジタルマーケティング
2019.06.25

日常化する“デジマ”
デジタルマーケティングはすっかり日常に定着した。“デジマ”という略称さえも幅広いビジネス領域で共有されている。デジマを活用しているのが、もはやデジタルに明るい一部のWebサービスや、消費者との接点をどこよりも強く求める消費材メーカーだけではなくなってきているからだ。
例えば、自社運営のECで商品を販売する中小企業や、事業者を顧客とするB2B企業でも、デジマの導入は進んでいる。当然、顧客サイドの目にもデジマの一端は映り込む。行動に合わせて広告表示が変わったり、今いる位置に合わせてプッシュ通知が来たり。デジマはすでに日々の体験の中に溶け込んでいる。
データ“量”依存のデジマが見せる“限界”
一方、GAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)に対する規制の議論も続いている。デジタルの日常化が進む裏で、大量の個人データが使われていることも明らかになった。「そこまでしていたのか」という驚きはあったものの、日々の体験から「それくらいのことはやっているだろうと思っていた」という納得感もある。規制議論を見つめる多くの人は、そうした妙な感覚を味わっているに違いない。
では、デジマを実際に行っている現場は今、何を思うのか? 実のところ、「ビッグデータさえ集めれば勝ち」などという分かりやすい話ではなくなっている。特定の業界を除けば、「大量の行動データだけでユーザーの将来の行動までを予測」することには無理があるからだ。少なくとも、売上に直接的なインパクトを与えることは難しいと言わざるを得ない現実に突き当たっている。
“利用シーン”という手がかり
行動データを大量に集めるだけでは限界がある、とはいうものの、例えば顧客の利用シーンが限定的で、なおかつ顧客の動きを想定しやすい業界だった場合は、少々話が違う。化粧品や健康食品の単品販売などがわかりやすいだろう。これらのカテゴリーでは、初めて買ってくれた顧客がその商品を使い終わるタイミングというのを見通すことができる。つまり、次の購買機会を見通せる。使い終わるタイミングを見計らい、定期的な購買を促進するキャンペーンをメールやプッシュ通知を送り、固定客化していくアプローチが可能だ。過去の購買履歴データに基づくデジタルマーケティングで効果を出していくことができる。
裏を返せば、利用シーンがバラバラな業界の場合、顧客が何をいつ必要とするのか、その動きを想定するのが難しくなる。例えば、メガネを買った人が、次にメガネを買うタイミングはいつになるのか? メガネの場合、購買動機は人それぞれである。オシャレのため、花粉症の対策のため、レンズの度が合わなくなったから……。動機次第で、次の購買タイミングは大きく変わることになる。「オシャレしたい」という意向の強い顧客ならば、そのタイミングはすぐにでも訪れるかもしれない。しかし、花粉症対策のためにメガネを購入する人だった場合、買い換えるタイミングは何年も先のことになるかもしれない。化粧品や健康食品と同じアプローチでは、なかなか効果を見込めない。
パーソナライゼーション発想は“希望の光”?
デジタルマーケティングは、短期間の内に3つの発展段階を経てコンセプトを洗練化してきた。
(1)顧客とのコミュニケーション機会を増やすタッチポイント・コンテンツを拡充しよう
(2)顧客の行動データや外部データといったビッグデータの活用を進めていこう
(3)顧客ひとりひとりに合わせたコミュニケーションの最適化=パーソナライゼーションを徹底しよう
以上のビッグデータ活用のフェーズを1つひとつ踏みしめてきた現場では、“パーソナライゼーション”というコンセプトが盛んに叫ばれている。商品やサービスを個別の顧客に合わせてカスタマイズする“マスカスタマイゼーション”という言葉もしばしば登場する。
“カスタマージャーニー”や“ペルソナ”という単語も、今やデジマ界のバズワード的存在になっている。パーソナライゼーションでは、特定の顧客になり切って、顧客の動きを「妄想」することに重点を置く手法をとるが、具体的にはペルソナという仮想顧客を想定。このペルソナの目線に立って、商品・サービス購買までの動きを想定するのがカスタマージャーニーだ。そしてこのジャーニーをもとに、顧客を先回りして待ち構え、1回だけのアプローチではなく、いくつものアプローチを積み重ねていく。そのため、こうした手法や戦術をシナリオと呼ぶケースも多い。
けっこう辛い。パーソナライゼーションのしくじり先生
デジマにおける「量の力学の限界」を超えるうえで、パーソナライゼーションを希望の光のように感じている現場は少なくないし、決して否定はしないが、考えれば考えるほど辛くなるのもパーソナライゼーションの特徴といえる。
リアリティのあるペルソナやカスタマージャーニーを作ることができたなら「個」客へのアプローチもできてしまいそうではあるが、実際の現場では、ターゲットとなる顧客をリスト化するために絞り込みの軸を用意する。そこでペルソナを忠実に絞り込もうとすればするほど、どうしても絞り込みの軸が多くなり過ぎてしまいがちだ。「絞り込み過ぎたペルソナ」に従えば、当然のことながらアプローチできる顧客の絶対数は少なくなる。どんなに有効なアプローチを用意しても、対象の数が少ないのだから、やってもやっても売上が伸びないことになる。
ではどう対応するか? 売上を確保しようと考え、いくつものシナリオを作ることになる。「徹底して絞り込んだペルソナ」が1つしかない場合は売上に限りがあるとしても、異なる複数のペルソナを用意して、それぞれに有効な打ち手を実行すれば、売上の問題は解決するはず。そういう理屈が机上では成立する。ところが、現場のマーケターの実情はといえば、クリエイティブのチェックやコンプライアンスへの対応に日々追われている。その中で、たくさんのシナリオを作って、実行していくのはけっこう辛い。
こうして「現実味のない机上の戦略」として現場から退けられた場合、結局は「1つのシナリオ」路線に戻っていく。「1つしかないシナリオでもカバーできる範囲を広げれば良いじゃないか」という発想だ。だが、もし今そういう局面に到達している人がいるのなら、よーく考えて気づいてほしい。「それって、言い換えたら『パーソナライゼーションをあきらめて、万人受けするアプローチに戻っちゃいました』ということだよね?」と。進化は失敗(しくじり)の向こう側にしかない。思った通りにはいかないデジマだが、希望が見えているのは事実。このジャーニー(試行錯誤)は、ともかく続けていくしかない。